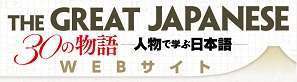セミの「なき声」
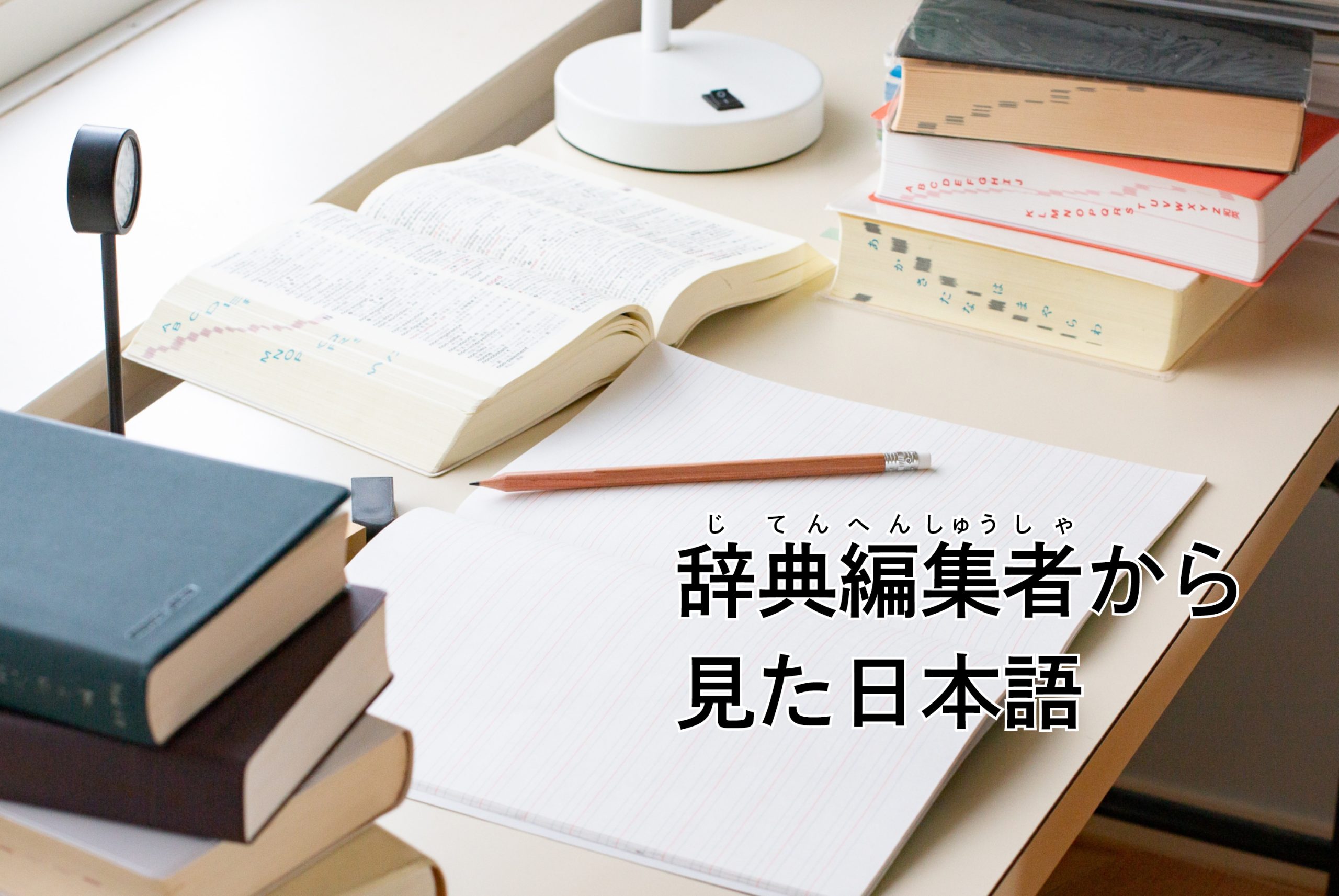
夏になると、日本では林や森の中だけでなく、人が住む町でも、セミのなき声がさかんに聞こえてきます。セミは木の上の方にとまって、大きな声でなく虫です。

セミ
今、セミの「なき声」と書きましたが、セミの「なき声」とよばれている音は、実際には口から出る「声」ではありません。おなかのあたりに音をならす部分があるのです。
日本で「なき声」を聞くことができるおもなセミは、ニイニイゼミ、アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシなどです。
ニイニイゼミは「なき声」がニーニーとかチーチーとか聞こえることから、ニイニイゼミという名前が付けられました。
アブラゼミの「なき声」はジージーと聞こえますが、この音は油がにえる音に似ていることからこの名が付いたといわれています。
ミンミンゼミの「なき声」はミィーンミンミンと聞こえます。やはり「なき声」から付けられた名前です。
クマゼミは、シャー、シャーとなきます。大きなセミで体がクマのように黒くてかたいので「クマ」という名が付けられました。
ヒグラシの「なき声」はカナカナと聞こえるので、カナカナ(ゼミ)ともいいます。
ツクツクボウシの「なき声」はオーシツクツクと聞こえ、名前も「なき声」からです。
このようなセミたちがさかんになくようすを表す語もあります。「せみしぐれ」です。「しぐれ」というのはふったりやんだりする雨のことをいいます。「せみしぐれ」は多くのセミがさかんにないて声が大きくなったり小さくなったりして、まるで雨の「しぐれ」がふる音のように聞こえることから生まれた語です。
ところでセミの「なき声」をきくと、多くの日本人が思い出す俳句があります。江戸時代(1603年〜1868年)の松尾芭蕉という人が作った俳句です。
「しづかさや岩にしみ入るせみの声」
というものです。

この俳句が詠まれたお寺(立石寺)
意味は、何という静かさだろう。この静かさの中に、ふとセミのなき声が聞こえて、まるであたりの岩山に深くしみとおって行くような気がする、というものです。作者の松尾芭蕉も、自分の心がこの静かさの中に深くしみとおって行くように感じているのです。
セミは、夏の季節の日本ではあちこちで「声」をきくことができる、代表的な虫なのです。
文:神永曉
写真:写真AC
音源提供:Springin’ Sound Stock
(2025.6.20)