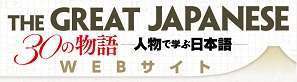《朝顔狗子図杉戸》(1784年)
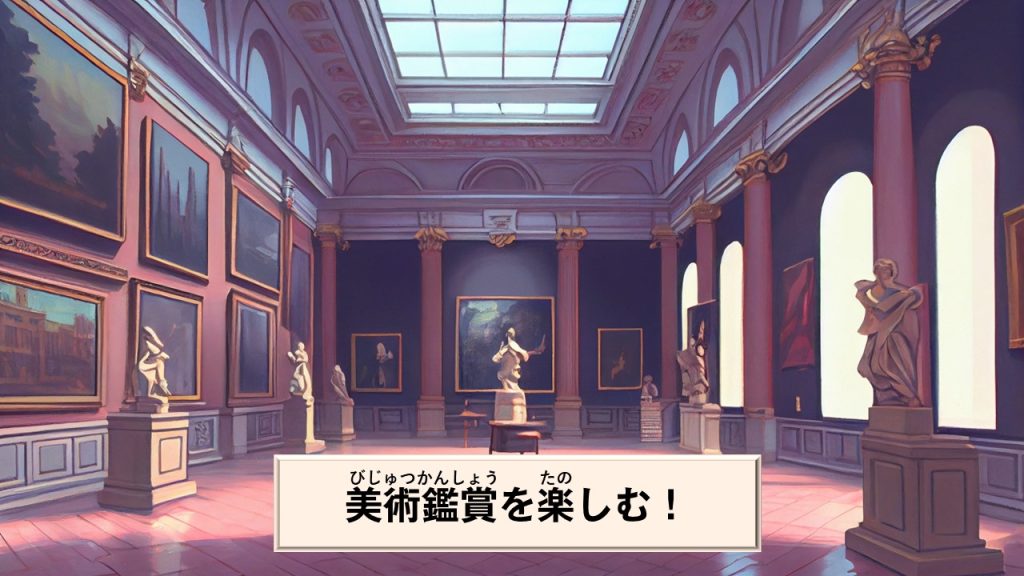


この絵は、円山応挙(1733年〜1795年)の《朝顔狗子図杉戸》です。円山応挙は江戸時代(1603年〜1868年)中期に京都で生まれた絵師で、近・現代にまで続く「円山派」と呼ばれる流派を作り上げ、京都画壇で多くの弟子を育てました。写生を重視して、いつも写生帳を持ち歩き、時間があればスケッチをして、若冲と同じように動物、植物、昆虫などを客観的に詳しく描いていました。

円山応挙肖像(谷文晁『近世名家肖像図巻』より)
この《朝顔狗子図杉戸》は、愛知県の明眼院というお寺の書斎の戸として1784年に制作されました。左側の戸に2匹、右側の戸に3匹のコロコロと太った可愛らしい子犬が庭で遊んでいる様子を描いています。季節は夏から秋でしょうか。庭には青い花と緑の葉が美しい朝顔が咲き、右側の戸の3匹の子犬たちのうち、2匹はじゃれあって、その横で白い犬が2匹を微笑ましく見つめています。


左側の戸の茶色い子犬は、その朝顔のツルをくわえて遊んでいます。ちょっといたずらをしているのがわかっているような目が可愛いです。その左の白い犬は後ろ足で首をかいています。その足の裏には土がついており、子犬たちが外にいることだけでなく、朝顔が小さく描かれることで、子犬の大きさもよくわかります。


応挙は、特に子犬が好きだったのか、頻繁に描いていたようですが、掛け軸ではなく杉戸に描いているのは、珍しいそうです。また、杉戸全体から見ると、子犬と朝顔のモチーフは下部に描かれていて、見る人が立つ地面につながっているように感じます。この絵が描かれた明眼院というお寺は、目の病気の治療を行っており、その治療に来る子供たちの視線に合わせて描かれたのかもしれません。応挙の愛情に満ちた気持ちが伝わってきます。応挙の絵は、その優れた絵画技術だけでなく、親しみやすい画風から多くの人に好まれました。《朝顔狗子図杉戸》は現在、東京国立博物館に所蔵されています。