日本の城
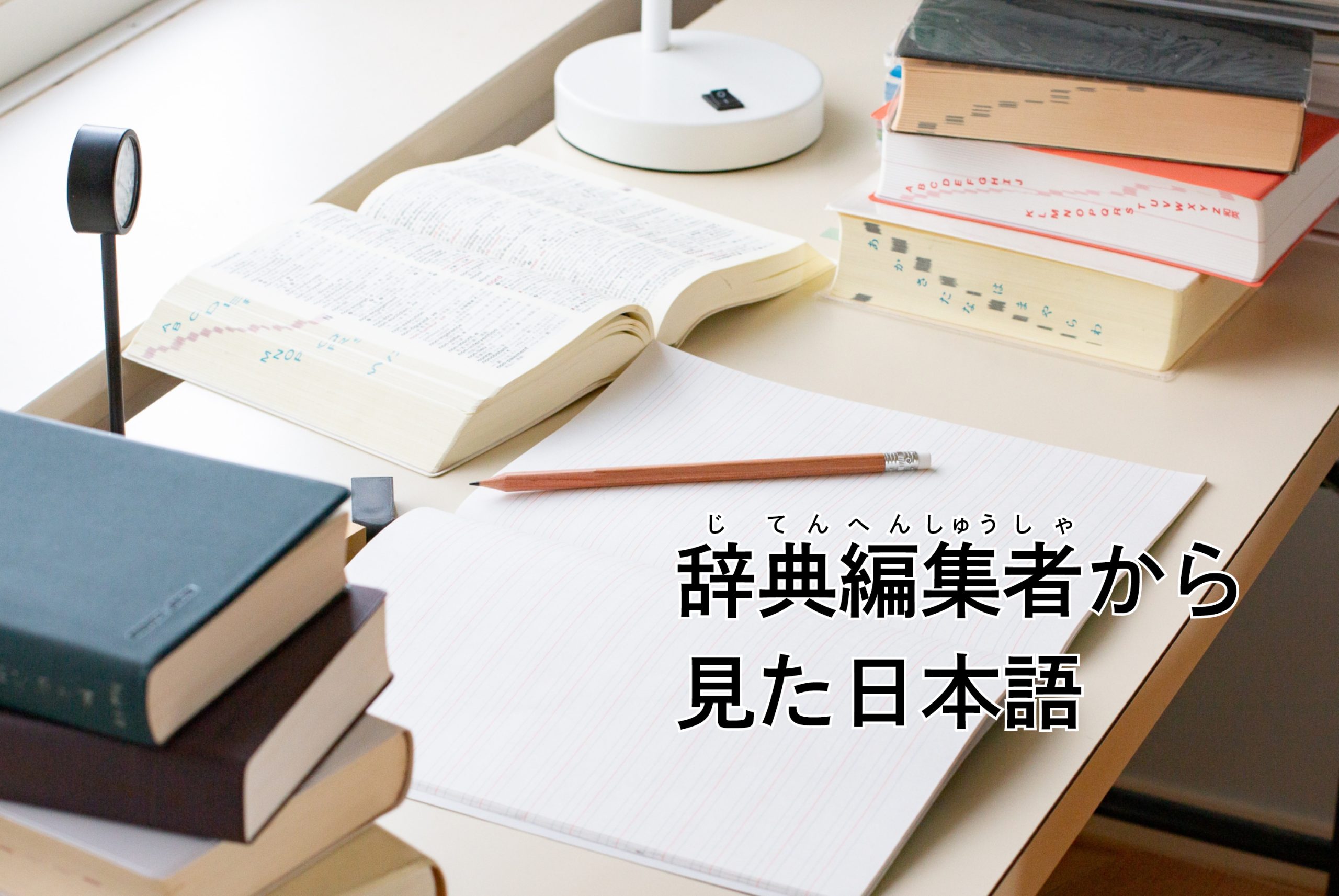
日本には、むかし建てられた城が各地にたくさん残っています。城とは敵の攻撃を防ぐための施設です。現在残っている城は、ほとんどが日本の戦国時代からあとに建てられたものです。戦国時代とは、1467~1477年に京都とそのまわりで「応仁の乱」という戦いが起きますが、その戦いからあとの約100年間をいいます。この100年間に、京都だけでなく日本の各地では戦いがさかんに起こりました。そのときに、城はとても重要な役割を果たしたのです。

日本の城(松本城)

岐阜城

岐阜城から見える景色
城には天守閣がありましたが、ほとんどの天守閣は明治時代(1868〜1912年)になってこわされてしまいました。現在天守閣のある城は、多くが昭和時代(1926〜1989年)になってから建て直されたものです。新しく建てられた天守閣には、コンクリートで作られたものもたくさんあります。

姫路城
城は敵の攻撃を防ぐために作られたものですから、そのためにさまざまな工夫がされています。
城は、堀、石垣などによっていくつかの部分に分けられています。その部分を曲輪と言います。堀は城のまわりにある、池のようになっている所を言います。
石垣は石を積み上げて、他の部分と区別できるようにしたところです。石垣の中には、大きな石を見上げるほど高く積み上げているものもあります。そこで使われている石の大きさはばらばらで、そのような石を積み上げて、よくくずれないものだと感心させられます。

堀と石垣

石垣の石の大きさはばらばら
天守閣の近くには、城主という城の主人が住む家もあり、ここが城の中心となるところです。ここを本丸と言います。「丸」は城を構成する部分の呼び名です。本丸の外側には、二の丸、三の丸とよばれる部分があります。この本丸、二の丸、三の丸などの位置は城ごとに違います。
城では、中に入ってきた敵の兵士がまようように、あちこちにまがった通路を作るなどして、どうしたら守りやすいかを考えて作られています。

石垣でできた通路がまがっている
文:神永曉
写真:写真AC/岡野秀夫
(2024.4.16)
