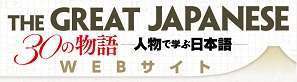神輿
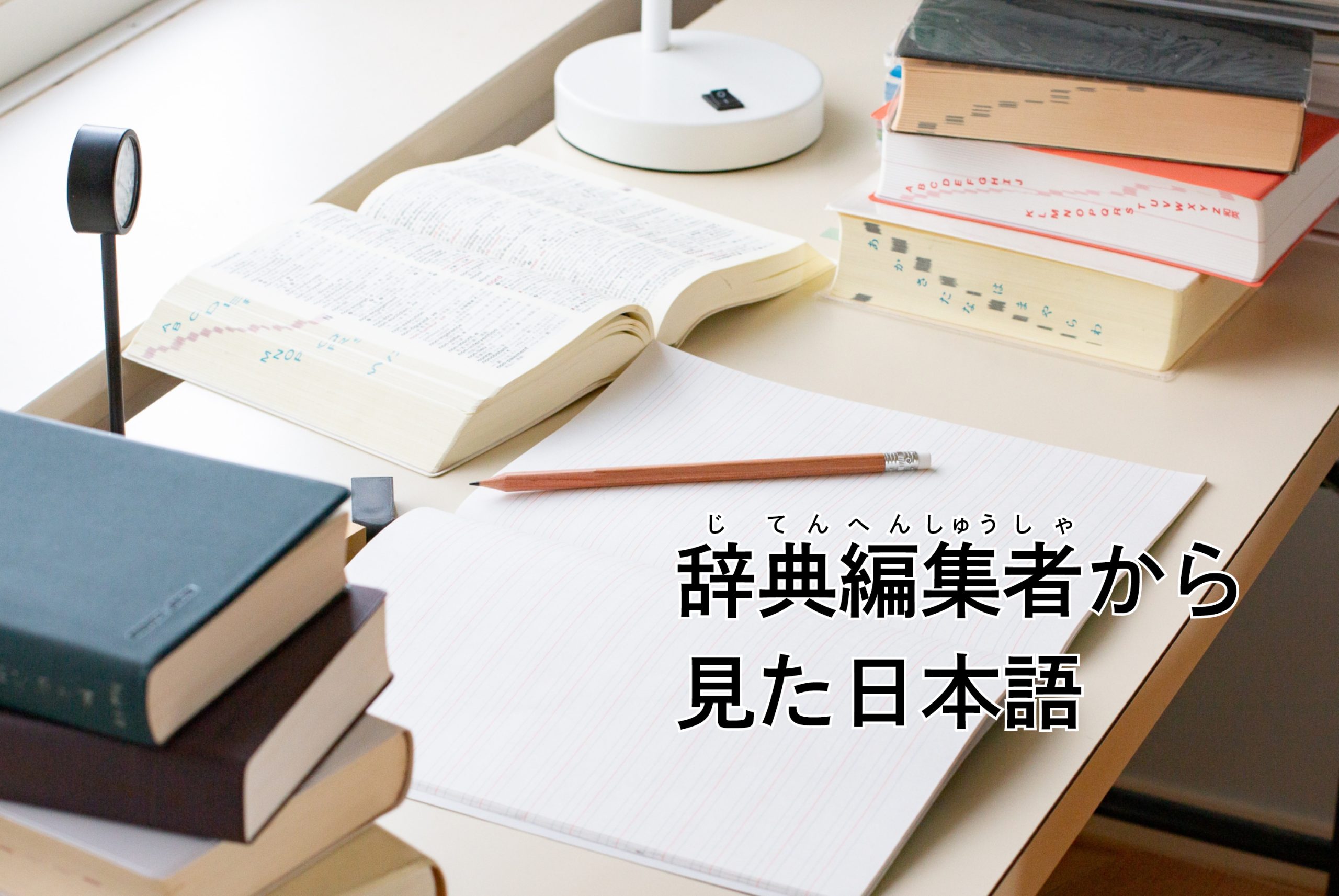
神社のお祭りでは、小さな神社の建物のようなものを上にのせた台を大勢の人がいっしょに肩にかついで、町の中を歩いて回ります。この台を、「みこし」と言います。さらに「お」を付けて、「おみこし」とていねいに言うこともあります。

みこし
この台には神がのっていると考えられています。「みこし」は神社から出発して、人々が住んでいる村や町の中を神が回るためのものなのです。
台にはそれをかつぐための2本の棒がついています。「みこし」をかつぐ人は、ふつうはおそろいの「はっぴ」とよばれる上着を着ています。そして手ぬぐいをねじって頭に巻き、ひたいで結んだ「ねじりはちまき」というかっこうをしています。

みこしをかつぐ人々
「みこし」をかつぐときには、ふつうみんなで声をそろえて「わっしょいわっしょい」と大声を出します。「わっしょいわっしょい」ではなく、「そいやそいや」と言っている所もあります。そう言いながら、ふつうは「みこし」をゆらします。これは神がもつ力をたくさん出させるためです。「みこし」をゆらしながらかつぐ姿はとてもいさましく感じられます。
ただ神社によっては、「みこし」をゆらさずに静かにかつぐところもあります。最近では、「みこし」をかつぐ人が集まらなくて、トラックの荷台にのせて村や町の中を回ることもあります。
この読みものの最初で「みこし」は小さな神社の建物のようなものを上にのせたものだと書きましたが、じつはほかにもさまざまな形のものがあります。たとえば子どもがかつぐ「みこし」の中には、酒の入っていないたるを台にのせたものもあります。
「みこし」どうしをはげしくぶつけ合う祭りもあります。中でも広島県福山市の素盞嗚神社のものが有名です。
「みこし」の「こし」は神や人をのせる台のことですが、人間の体の部分で、体を回したり曲げたりする部分の「腰」と同じ発音です。そのため「みこし」は「腰」を意味することもあり、それを使った決まった言い方もあります。
たとえば、「みこしを上げる」は、長くすわっていた腰をあげる、つまり立ちあがるという意味です。「みこしを上げてそのあたりを歩こう」などと使います。また、なにかにとりかかる、仕事をはじめるという意味でも使い、「昼休みがおわったのでみこしを上げる」などといいます。
「みこしをすえる」は、その場にすわって動かない、ゆったりとかまえておどろいたりあわてたりしないという意味です。「みこしをすえて長々と話をする」のように使います。

みこしをすえて長々と話をする
「みこしをかつぐ」は、他人をおだてあげる(しきりにほめてその気にさせる)という意味です。人をおだてることを「もちあげる」「かつぐ」とも言いますが、それと同じ意味です。「みこしをかついで会の代表にする」などと使います。

みこしをかつぐ
夏が近づくと、各地の神社でお祭りをおこなうところが増えてきます。5月におこなわれる東京浅草の浅草神社の三社祭は、大勢の人がたくさんの「みこし」をはげしくゆらしながらかつぐので有名です。そのようすはインターネットでも公開されていますので、興味がありましたらぜひ見てください。
文:神永曉
写真:写真AC/Adobe Stock
イラスト:イラストAC
(2025.2.21)