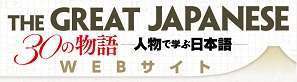春の俳句②

春の俳句の2作目です。俳句における「春」は、今でいうと、だいたい2月から4月のことをいいます。それをイメージして読んでみてください。
「雪とけて村いっぱいの 子どもかな」小林一茶
どんな様子が目に浮かびますか。
長く厳しい冬が終わり、待ちに待った春。村全体を覆っていた雪がとけ、喜んだ子どもたちが外へ飛び出して、元気いっぱい遊んでいる様子でしょうか。春の暖かな日差しの中、子どもたちの笑い声が聞こえてくるようです。

この俳句を詠んだ小林一茶(1763年~1827年)は、どんな人物だったのでしょうか。
一茶は今の長野県の農家に生まれました。一茶が3歳のときに母が亡くなり、8歳のときに父が再婚しましたが、新しい母親(継母)とはうまくいかなかったようです。15歳のときに、働くために江戸(今の東京)に行かされ、そこで俳句に出合い、俳句を学び始めました。その後、一茶は様々な土地を旅しながら、俳人たちと交流を続け、作品を句集として出版したりしました。39歳で故郷に帰って病気の父を看病しますが、残念ながら父は亡くなってしまいます。父の遺産をめぐって、10年以上、継母や弟たちと争いが続いたといいます。
父の死後、一茶は江戸で暮らしていましたが、50歳のとき、再び故郷に帰ります。「雪とけて~」の俳句は、このときに詠まれたものです。一茶の故郷は雪がかなり降る地域で、大人も埋まってしまうほどでした。

それほどの雪の季節が終わったのですから、外を走り回りたくなるような気持ちもわかるような気がしますね。
一茶が生きた時代は今と違って、冬の山の暮らしは厳しいものでした。十分な食べ物もなく、栄養不足や寒さによって子どもが亡くなることもあったようです。だからこそ、春になり、子どもたちの明るい笑顔や楽しげな笑い声に、一茶は喜びでいっぱいになったのでしょう。

一茶は52歳で結婚しますが、子どもも妻も早くに亡くなってしまいます。継母や弟たちとの争いや、子どもや妻の死などつらいことの多い人生だったようですが、一茶はその生涯で約2万句もの俳句を残しました。
一茶の俳句は「生」をテーマにしているといわれ、子どもや小さな生き物、たとえば雀や蛙などを俳句に詠むことが多く、その作風は「一茶調」と呼ばれます。小さな命に対する温かさは、つらいことの多かった人生から生まれたのかもしれません。
文:新階由紀子
画像:写真AC/Adobe Stock
(2025.2.18)