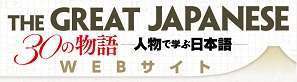豆まき
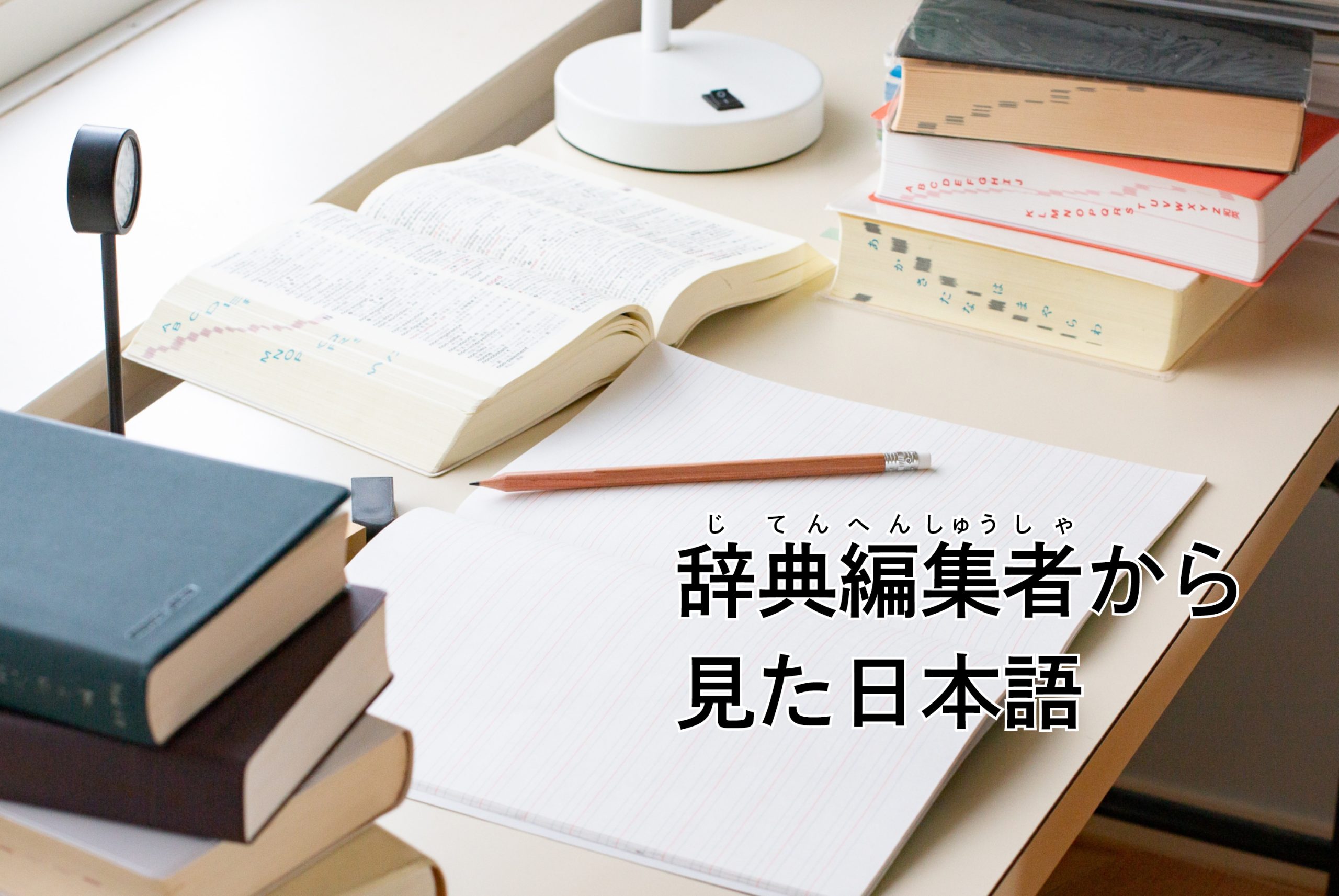
日本ではむかしから、「立春」とよばれる日が春の始まりだと考えられてきました。それはいつごろかというと、年によって違いますが、だいたい2月4日ごろです。「立春」から春になるということは、その前の日までは冬だったわけです。
「立春」の前の日を、「節分」とよんでいます。「節分」とは季節が移り変わるときという意味ですが、この「節分」の日に各地の神社や寺、一般の家庭でも「豆まき」という行事をおこないます。


お寺や家での豆まき
「豆まき」では、ふつうなべなどに入れて火であぶった大豆を使います。最近は「豆まき」に使う大豆をお店でも売っています。なぜ大豆を使うのかよくわかりませんが、むかしから大豆には不思議な力があると考えられていたようです。ただ大豆ではなく、落花生をまく地域もあります。なぜ落花生をまくのかもよくわかりません。北海道や東北地方、九州の一部の県などでは落花生をまくことが多いようです。

豆まきでつかう大豆

落花生
「節分」のときに豆をまくのは、悪い病気を広める「鬼」をおいはらう行事がむかし宮廷(天皇が住んでいるところ)でおこなわれていたためです。豆をまきながら「鬼」をおいはらうときに、声に出して言うことばがあります。
「鬼は外、福は内」
というものです。意味は、鬼は家の外に出て行け、福(幸せ)は家に入って来いということです。
このことばもけっこう古くから使われていました。1447年に京都の寺のお坊さんが書いた日記にも「豆まき」のことが出てきます。明日は立春なので、あたりが暗くなってから火であぶった豆を部屋ごとにまいて「鬼外福内」の四字を口に出して言う、といった内容です。「鬼外福内」は「鬼は外、福は内」ということです。
室町時代(1336年~1573年)に生まれた「狂言」という劇の中に『節分』という題名の劇があります。こんな内容です。
節分の夜に、女がひとりでるすばんをしていると、そこに蓬萊という名の島から来た鬼がやってきます。鬼は女の美しさに心を奪われ、さかんに女に声をかけたり歌を歌ったりして近寄ってきます。でも女は相手にしません。反対に女は鬼のことばにしたがったように見せて、鬼が持っていた、着ると姿をかくすことができるという不思議な雨具や、ふるとほしいものをなんでも出せるという「うちでのこづち」という道具などを奪ってしまいます。そして女は「福は内へ、福は内へ、鬼は外へ、鬼は外へ」と言いながら豆をまいて鬼を追い出してしまうのです。
「鬼は外、福は内」は豆まきのときに口にする、おまじないのようなことばです。

昔の雨具

ところで、節分のときにまく豆を、自分の年齢の数だけ食べるという風習も古くからあります。年齢というのは、生まれた年を1歳とし、そのあと新しい年になると1歳ずつ年齢をたしていくものです。これを「数え年」といいますが、誕生日になったときに年齢を1歳足す数え方よりもふつうは年齢が1歳(誕生日までは2歳)多くなります。
私は10歳くらいのときに、豆まきの豆が大好きで年齢の数だけでは物足りなくてたくさん食べてしまい、お腹をこわして医者に行ったことがあります。お医者さんからはまじめな顔で、「豆を食べるときは年齢の数だけにしなさい」と言われました。今年私は、年齢の数だけ豆を食べるとすると、70個も食べなければなりません。
文:神永曉
写真:成田山新勝寺/写真AC/Adobe Stock
イラスト:イラストAC
(2025.1.28)